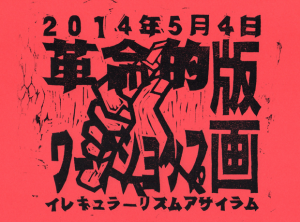正しい技法というものはない
少なくとも凸版形式の版画においては、その正しいつくり方などということを考えてみるのは、まず無意味なことである。
これは単にその外様性からのみいうのではなく、限られた個々の版種においても、その正しい技法などというものが、決して一つのルールとして決められる筈がないということである。凹版、平版の中には、いかんともしがたい化学的法則のあずかるプロセスもあって、たしかに薬品の使い方などある意味では正しい技法というものも必要ということになろう。しかし、それすらもある一つのプロセスを正しい技法の唯一の存在として理解するより、技術というものは実はその人の側にのみその時々に存在し、まったくそれは自由なものであるという理解のほうがはるかに重要なことではないだろうか。
技法は本来単純なものである
――しかしながら、現実に見る版画技術というものはひどく複雑な様相を呈している。
たとえば、日本の木版系の専門作家の中から適当に十人をとりだしてみよう。それがすぐれた作家であればそこにはすくなくとも十の異なったプロセスがある。それぞれにまったく自分勝手なものであるのに、人は驚くであろう。
これは、それぞれの作家が、個々の表現にもっとも適した効果を。自分なりにもっともたやすい手法によって求め、かつ多くの場合みずからそれを見出すということによって制作しているのが実状だからであろう。その一つがかなり面倒な手順を経るものであったとしても、それがみずから求めたものというところから、その意味するところはきわめて単純なものである筈だ。一見めちゃくちゃに見えても。それはその人にとって実に明快な意味をもった技法なのである。
それが、伝統的な木版画技術によったいわば古風なものであっても、みずからの肉体に墨を塗って紙面に押しあてたり、路上に拡げてマンホールの蓋を摺り取るといった新奇なものでも何でもかまわない。要するに、版画においても絵画としての表現がまず存在するのであって、それに版というものの効果と機能がプラスされること。そしてその表現内容と表現効果がもっとも単純にストレートに結びつくとき、そこに単なるプロセスとしてでなく、本来の技法というものの存在があるといってもよいのではなかろうか。
だから、正しい手法はない――ということはいいかえれば、技法とはまったく自由なものであり、その人その時に応じてすべてが正しい技法であり得るということ。技法は単純である――ということは、絵画としての版画技法はまたあらゆる可能性(プロセスとしては繁雑なものであってもいい)をもつべきものであるということなのである。
何もなくても版画はできる――ということも、したがって何をつかって、何をどうやっても(特別な用具材料がなくても)版形式の絵画的表現ができるということなのである。
『版画の技法』 凸版による技法 吉田穂高 美術出版社 昭和39年
 「
「